初代は、ここを参照してください。 <特記 2020/1/11> 2020/1/8に台風並みの強風があり、2代目ワイヤーアンテナがポッキリ折れてしまいました。その修理の備忘録です。ここを参照してください。 初代で使っていた、ルーフタワー(ローテータ付)と踏み台を撤去して、代わりにテレビアンテナ用の 屋根馬にポール(塩ビパイプ)を取り付けて、そのポールに釣竿アンテナ+AH-4を取り付けました。
 2代目は、垂直部分の竿にビニールコードを巻きつけています。(スパイラル巻き)
具体的には、竿の長さが6m18cmでビニールコードが7m50cmですので、ビニールコードのほうが長いので巻きつけることにしました。
初代は竿の長さが7m以上あったのでビニールコードを巻かずにも7m這わせることが出来ました。
AH-4の取説によるとエレメント(ビニールコード)は7m以上とあります。一方エレメントの長さは1/2λの整数倍にしては
いけないと言われています。
λ=300÷fの計算で(短縮率1.0)
300/7M=42.857→λ1/2=21.428 λ1/3=14.285 λ1/4=10.714 λ1/5=8.571 λ1/6=7.142 λ1/7=6.122
300/7.2M=41.666→λ1/2=20.833 λ1/3=13.888 λ1/4=10.416 λ1/5=8.332 λ1/6=6.954 λ1/7=5.952
各バンドの1/2λの整数倍の波長(短縮率0.95)
(300/3.5M)*0.95=81.428 →λ1/10=8.142 λ1/11=7.402 λ1/12=6.785
(300/7M)*0.95=40.714 →λ1/5=8.142 λ1/6=6.78
(300/10M)*0.95=28.500 →λ1/3=9.500 λ1/4=7.125 λ1/5=5.700
(300/14M)*0.95=20.357 →λ1/3=6.785
(300/21M)*0.95=13.571 →λ1/2=6.785
(300/24M)*0.95=11.875 →λ1/2=5.937
(300/28M)*0.95=10.178 →λ1/2=5.089
(300/50M)*0.95=5.700
エレメント長7.5mは、上記計算結果から全バンドでOK
※1/2λの整数倍の波長(短縮率0.95)が7.5mと一致していない
<入手釣竿>
釣竿アンテナ (釣覇10)
グラスファイバーの14本繋ぎ全長約8m
(先端1mmΦ 手元30.5mmΦ)
2019/8末時点では無いようですが、釣竿アンテナ (釣覇90)13本繋ぎ全長約7.1mはあるようです。
<購入先>
Yahooショッピング
購入ストア:チタンシステム
4,200円(送料700円)
2代目は、垂直部分の竿にビニールコードを巻きつけています。(スパイラル巻き)
具体的には、竿の長さが6m18cmでビニールコードが7m50cmですので、ビニールコードのほうが長いので巻きつけることにしました。
初代は竿の長さが7m以上あったのでビニールコードを巻かずにも7m這わせることが出来ました。
AH-4の取説によるとエレメント(ビニールコード)は7m以上とあります。一方エレメントの長さは1/2λの整数倍にしては
いけないと言われています。
λ=300÷fの計算で(短縮率1.0)
300/7M=42.857→λ1/2=21.428 λ1/3=14.285 λ1/4=10.714 λ1/5=8.571 λ1/6=7.142 λ1/7=6.122
300/7.2M=41.666→λ1/2=20.833 λ1/3=13.888 λ1/4=10.416 λ1/5=8.332 λ1/6=6.954 λ1/7=5.952
各バンドの1/2λの整数倍の波長(短縮率0.95)
(300/3.5M)*0.95=81.428 →λ1/10=8.142 λ1/11=7.402 λ1/12=6.785
(300/7M)*0.95=40.714 →λ1/5=8.142 λ1/6=6.78
(300/10M)*0.95=28.500 →λ1/3=9.500 λ1/4=7.125 λ1/5=5.700
(300/14M)*0.95=20.357 →λ1/3=6.785
(300/21M)*0.95=13.571 →λ1/2=6.785
(300/24M)*0.95=11.875 →λ1/2=5.937
(300/28M)*0.95=10.178 →λ1/2=5.089
(300/50M)*0.95=5.700
エレメント長7.5mは、上記計算結果から全バンドでOK
※1/2λの整数倍の波長(短縮率0.95)が7.5mと一致していない
<入手釣竿>
釣竿アンテナ (釣覇10)
グラスファイバーの14本繋ぎ全長約8m
(先端1mmΦ 手元30.5mmΦ)
2019/8末時点では無いようですが、釣竿アンテナ (釣覇90)13本繋ぎ全長約7.1mはあるようです。
<購入先>
Yahooショッピング
購入ストア:チタンシステム
4,200円(送料700円)

 <エレメント>
ビニールコード
外形3mmの心線1.25のより線
<ポール>
ホームセンターで購入
塩ビパイプ 外形32Φ 1m
最先端のビニールコード処理
<エレメント>
ビニールコード
外形3mmの心線1.25のより線
<ポール>
ホームセンターで購入
塩ビパイプ 外形32Φ 1m
最先端のビニールコード処理
 エレメントは14本の内10本(6m18cm)を利用してつなぎ目に結束バンドし、その上にビニールテープを巻きつけている(7〜10cm間隔)
エレメントは14本の内10本(6m18cm)を利用してつなぎ目に結束バンドし、その上にビニールテープを巻きつけている(7〜10cm間隔)

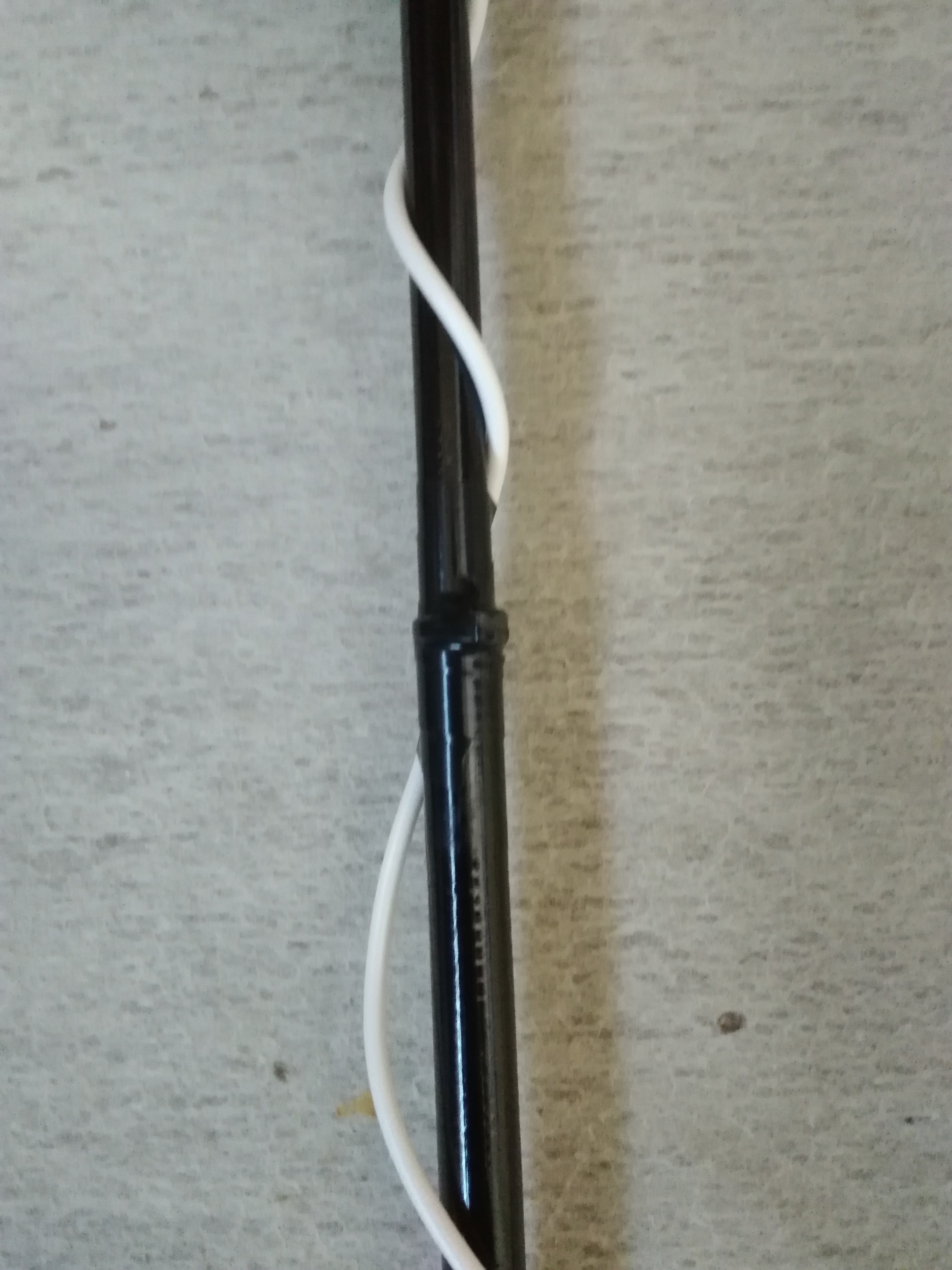 アース線は、以前のもをそのまま利用(白、黒のビニールコード)
アース線は、以前のもをそのまま利用(白、黒のビニールコード)
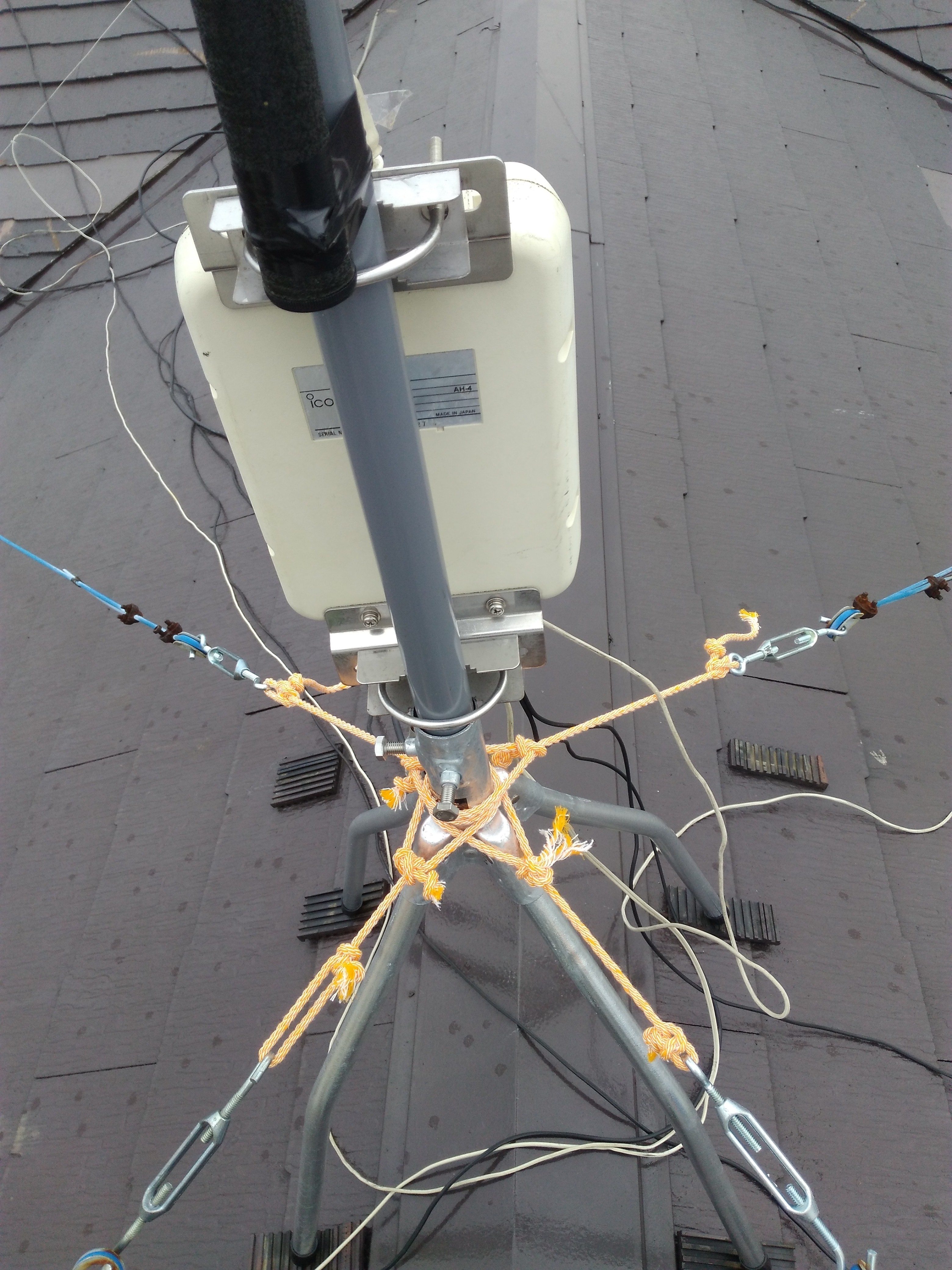
 <各バンドのSWR測定>
主にCW運用ですので、CW周波数で測定しました。全バンド2.0以下となりました。
初代に比べてかなり良くなりました。予想以上の結果でした。
エレメントの長さが7.5m(初代は7m)にしたからでしょうか(0.5mの差が効いた)
スパイラル巻きにして全長が6.18mになっても大丈夫と言う結果も得られました。
3.5M(3.505):1.10
7M(7.10) :1.25
10M(10.130):1.18
14M(14.050):1.45
18M(18.080):1.85
21M(21.050):1.20
24M(24.900):1.20
28M(28.050):1.85
50M(50.050):1.50
50M(52.350):1.10
追記 2019/9/2
アース線を約6m1本追加
その結果、10MでSWRが1.0に3.5Mも回り込みが少なくなりました。
しかし、7Mが1.25 → 1.45に上がってます。
3.5M(3.505):1.10 → 1.20
7M(7.10) :1.25 → 1.45
10M(10.130):1.18 → 1.00
14M(14.050):1.45 → 1.50
18M(18.080):1.85 → 1.65
21M(21.050):1.20 → 1.20
24M(24.900):1.20 → 1.20
28M(28.050):1.85 → 1.20
50M(50.050):1.50 → 1.15
50M(52.350):1.10 → 1.35
<各バンドのSWR測定>
主にCW運用ですので、CW周波数で測定しました。全バンド2.0以下となりました。
初代に比べてかなり良くなりました。予想以上の結果でした。
エレメントの長さが7.5m(初代は7m)にしたからでしょうか(0.5mの差が効いた)
スパイラル巻きにして全長が6.18mになっても大丈夫と言う結果も得られました。
3.5M(3.505):1.10
7M(7.10) :1.25
10M(10.130):1.18
14M(14.050):1.45
18M(18.080):1.85
21M(21.050):1.20
24M(24.900):1.20
28M(28.050):1.85
50M(50.050):1.50
50M(52.350):1.10
追記 2019/9/2
アース線を約6m1本追加
その結果、10MでSWRが1.0に3.5Mも回り込みが少なくなりました。
しかし、7Mが1.25 → 1.45に上がってます。
3.5M(3.505):1.10 → 1.20
7M(7.10) :1.25 → 1.45
10M(10.130):1.18 → 1.00
14M(14.050):1.45 → 1.50
18M(18.080):1.85 → 1.65
21M(21.050):1.20 → 1.20
24M(24.900):1.20 → 1.20
28M(28.050):1.85 → 1.20
50M(50.050):1.50 → 1.15
50M(52.350):1.10 → 1.35